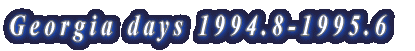
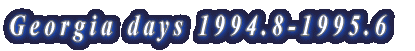
| 最終話 「別れの日」 |
| 6月8日(木)、帰国前日。朝からケネディー先生とアトランタに買い物へ。とにかくあらゆる人たちへのお土産を買わなければならず、デパートや商店街などを走り回った。そして帰りは渋滞し、ダウンタウンから郊外のケネソーに行くまで通常15分くらいなのに、1時間も掛かってしまった。ケネソーのモールに行きCDなどを買ったが、とにかく時間がなく、明日空港で何か買えたらと途中で諦めた。 夜はお別れパーティー。ケネディー先生、クローフォード先生、バートン先生(いつもの3人組)、フィリップ、ミリン、ミリンの叔父さん、ワーレン、エイドリアン、ペイジ、デスカ、エイヴェイットが来てくれた。本当はもっと会いたい人たちがいたのだが、残念ながら都合が付かないようだった。更にはベリンダの友達“チャイナ・ドール”ことロンダも来た。 「あなたと会えなくなるなんて本当に寂しいわ・・・。記念に写真撮りましょ!ソファーで私を抱きしめてちょうだい!」 なんとまぁ大胆にも物凄い写真を撮ってしまった。しまいには、ブチューッとキスまで受けた。 愉快な夜だった。皆笑顔で楽しんだ。フィリップは相変わらずいたずらをしてきて、僕の背中に氷を入れたり、写真を撮る時にヘンなポーズをとったり、最後の最後を楽しんでいた。クローフォード先生は、授業を一時間潰してダンスレッスンした思い出を語り、その時の踊りを再現した。ミリンはテストの結果が最悪で、リサーチが38点、アメリカ史が51点だったと言い、僕は他人事のように笑っていた。皆、いつも通りに愉快だった。ベリンダはこの日の為にケーキを用意してくれていた。“We'll miss you, Ko”(寂しくなるよ、コウ)とメッセージが載っていた。 「パーティーには行かない、プレゼントも買わない」と言っていたフィリップは、アトランタ・オリンピックのTシャツを買って来てくれた。箱に“YOUR GO AWAY GIFT!!!”(出て行けギフト!!)と手書きで書かれた紙が貼られていた。クローフォード先生はこの辺りの昔の風景が描かれたポストカードのセット、バートン先生は帽子をくれた。 深夜になり、賑やかなパーティーはいつの間にか終わりに近付いていた。皆との別れの時が来ても、自分が明日には帰国するということを実感出来ないでいた。いつものように大笑いし、皆の笑いが絶えないパーティーだった。この時間が永遠に続くのではないかと錯覚するほどに、あと少しで皆とは別れなければいけない時間が来ることをまるで知りもしないかのように笑い続けていた。・・・しかし、残酷にもその刻はやってきた。フィリップは車に乗り込む前に、いつもの調子で僕に別れを告げた。 「コウ、明日の朝、君の夢は見ないよ。明日は泣くんじゃないぞ!」 「きっと泣く!」 「カードの裏に住所を書いておいたから」 「え、何、手紙書いてくれんの?」 「たぶんね」 筆不精のフィリップが“手紙を書く”などとは思えなかったが。 皆がいつもの笑顔で去って行く。そう、また明日学校で会うかのように。いつものように、僕たちはまた明日学校で会い、冗談を言い合って大笑いするのだ。しんみりとした別れが僕には似合わないのは分かっていた。 「寂しくなるわ!コウ!」 バートン先生の声が聞こえた。何の意味も成さない、ただの音に聞こえた。なぜ、寂しくなるなんて言うのだろう?昨日も今日も明日も変わらないはずなのに、明日も会えるはずなのに・・・。皆が僕の視界から消えて行き、玄関先にひとり取り残された時、僕はようやく明日には帰国するのだという実感を持ち愕然とした。ひたすら「寂しい」と感じた。昨日と今日は同じでも、今日と明日は違うのだ。昨日も今日も僕はここの住人だったけれど、明日からはもうここにはいない。あの学校には二度と通わない。この愉快な先生たちの授業を受けることもない。フィリップに「家に居たくないから遊ぼうよ」とせがむこともない。ケネディー先生に「ヒマだからどこかに連れてってよ」とわがままを言うこともない。これまでの日常は全て消え去り、過去になるのだ。 どうしようもない気持ちを抱えて、僕は自分の部屋に入った。全てが終わった・・・。やっと終わったのだ。まだ残っていた荷造りをしながら、家を出る朝の4時まで僕は起きていた。もうこの先、二度と眠ることのないこの部屋で・・・。 6月9日(金)、朝4時に家を出た。空港へと向かう車の中で、ベリンダは運転しながらずっと喋り続けた。その横でデニーは眠っていた。途切れることのないベリンダの言葉に耳を傾けながら、僕は窓の外を不思議な気持ちで眺めていた。ここは僕の街。いや、他人の街。僕の街は、今向かっている遠い先にある。でも、確かにここは自分の街だった。 寝ていたはずのデニーがムクッと起き上がり、ロサンゼルスまではどこの航空会社の飛行機なのか訊ねてきた。 「ワォ〜!その航空会社は危ないんだぞ」 今、帰国しようとしている僕に向かって、そんなことしか言えないのかと僕は呆れ果てた。 「大丈夫よ!」 ベリンダが言った。 空港に着いて、デニーとベリンダと1枚ずつ写真を撮った。デニーとは握手しただけだったが、ベリンダは名残惜しそうに3回も抱き締めてきた。 「来年の夏、また戻って来るんでしょ?」 「うん」 「約束よ!」 「うん」 「友達も連れて来てね。手紙書いてね」 「でも、ベリンダ、貰った手紙は全部捨てちゃうんだよね?」 僕が大事に取っておいた手紙の山を見てベリンダは以前「アメリカ人は手紙なんて全部捨てるわよ」と言ったのだった。 「あら!あなたの手紙は捨てないわ!・・・じゃあ、元気でね」 「長い間お世話になりまして、どうもありがとうございました。さようなら、お元気で」 そして、朝6時に二人は空港から去って行った。僕はいつまでも二人の背中を見つめ続けていた。 国内便の飛行機の中ではずっと眠りこけていたが、ロサンゼルスからの国際便では日記帳を広げ、最後の留学日記を書いた。まだ留学して3ヶ月しか経っていないような気がしていた。ルイスヴィルから始まった嵐の1年が終わったのだ。夢にまで見たアメリカ生活は、僕に何を与えたのだろう。日本に帰ったら振り返ってみよう。あと数時間すれば、僕の体は自動的に日本に着いている。約1年ぶりの日本がすぐそこにある。まだ「明日も皆に会えるのではないか」という感覚を心のどこかに残しつつ、もうこの先書き込まれることのない日記帳を、そっと閉じた。 終 “その後” エピソード Vol.4 へ |