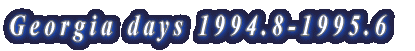
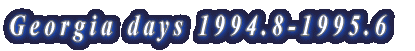
| エピソード Vol.2 「風向き」 |
| けたたましく電話が鳴った。真夏の夕暮れ時、悪いニュースを知らせるかのような音だった。僕は今でもあの音を忘れられない。 いよいよ明日、両親が東京に行って横田先生にお会いするという日だった。電話の呼び出し音が鳴った瞬間、僕の胸はざわついた。そしてそれは母も同じだったと思う。 「横田先生じゃない?」 僕も母も、根拠のない確信があった。母は急いで階段を駆け下り、電話を取った。僕は2階の部屋で、神妙な面持ちで母を待った。 「横田先生の娘さんが交通事故でさっき亡くなったって・・・」 衝撃を受けた。アメリカから夏休みで帰国し、友人たちと飛騨山脈に車旅行に出かけた娘さんの車が対向車に追突され、すぐ病院に運ばれたものの、お亡くなりになってしまった。 「娘さんが亡くなったというのに、凄く気丈で、しっかりとした話し方だった・・・」 横田先生がどんな想いで電話をしてきたのかと思うと、胸が詰まる思いだった。 両親の東京行きはキャンセルになり、その後、また横田先生とお会いするという機会には恵まれなかった。 それでも先生は、カリフォルニアにいる息子さんに、僕の為に学校の資料を集めてくれるよう頼んで下さり、全米の良質な私立高校のパンフレットが数校分届いた。両親は両親で、いろんな人たちに相談していたようだった。 「何も高校から行かなくたっていい。大学からでも決して遅くはない。どうしても行きたいというのなら、高校在学中に1年間の交換留学に行くという手だってある」 これが大半の人の意見のようだった。しかし、僕は一歩も譲らなかった。1年間の交換留学と、学校を卒業する正規留学とでは全く主旨が違う。アメリカの大学に進むのなら、アメリカの高校を出ていた方が何かと融通が利く。僕は日本の学校に進む気など更々なかった。息苦しいようなこの日本での焦燥感は、アメリカに行けば解消されると僕は安易に考えていたのだ。 夏が過ぎ、秋が来た。そろそろ進路を決めなければいけない時期になっていた。 「本人の意志が強すぎて・・・アメリカに行かせても、もういいのではないかと思っている」 祖父母宅で食事をしていた時の、父の言葉だった。嬉しい言葉ではあったが、どこか引っかかった。100%の賛成で言っている言葉ではないような、いや、その先のことを僕が感知して、行ってもいいと言われているのに「アメリカには行けないのではないか」という気持ちをどうしても拭うことは出来なかった。 間もなくして、衝撃的なニュースが日本中を駆け巡った。服部君事件である。10月末のハロウィーンの日、アメリカに留学していた服部君が、「フリーズ」(止まれ)と言われたのを「プリーズ」(どうぞ)と勘違いして、銃で撃たれて亡くなった。銃社会のアメリカの現実を突き付けられた両親は、これをきっかけに何が何でも反対を押し通すようになった。 「羽黒高校の国際コースに行っても構わない。そこで1年間の交換留学なら認める。卒業したら、アメリカでもどこでも、好きなところに行っていい」 両親の懇願に僕は従わざるを得なかった。 元々、私立はダメだと言われていたのだ。公立高校の受験しか認めないと父は言っていたのに、私立である羽黒高校の受験を許可してくれた。これは親が譲歩した結果だった。国際コースに入学すると、外国人教師による英語の授業を始め、国際人育成の為のカリキュラムが用意され、2年次の夏休みには1ヶ月間アメリカ語学研修、そして希望者は1年間の交換留学が認められ(単位も換算出来るので、留年せずに済む)、外国の大学への進学指導もしている、当時にしては珍しい独特なコースであった。 頭を切り替え、羽黒高校国際コースについてじっくり調べていくうちに、興味も沸いてきた。どんな未来が待っているのだろう。少なくとも、今の状況よりは良くなるに違いない。とは言え、羽黒高校を受験、合格し、あとは入学を待つのみとなっていた時期でさえ、ふと虚しさに襲われることがあった。なんで僕はアメリカの高校に進むことが出来なかったのだろう・・・。考え出すと苛々と虚しさが胸一杯に広がり、止まらなくなってしまう僕は、母に八つ当たりをすることもあった。 しかし結果的に、両親が提示したこの道は正解であった。羽黒高校国際コースには個性的なメンバーが勢揃いし、個性が重視された。異端児扱いだった僕の個性が開花していくような感じがした。人の個性というものは、自分ひとりだけで開花させることは出来ない。周囲によって、それが上手く出て行き花開くもの、僕は初めてそれを知った。強い個性が当たり前、という日常を僕は謳歌した。得意な英語を伸ばす努力も認めて貰える環境に感謝した。 入学してすぐに留学希望があるのかどうか、そして進路についても訊かれた。当初の予定通り、僕は「卒業後は米国の大学に進みたい」と言った。すると先生は次のように僕に語った。 「アメリカの大学ならいつでも行ける。でも日本の大学は、アメリカのようにいつでも誰でも受け入れるという体制は取っていないから、今しかチャンスがない。アメリカの大学は日本の大学を卒業してからでも行けるけど、その逆は難しいよ。よく考えてみて」 その言葉に、なぜか僕は素直に頷き、とても素直に受け入れた。ほんの数日前までアメリカに燃え盛っていた僕が、その先生の短い言葉だけで、日本の大学に進学することをあっさり決めたのだ。でも先生の言葉はきっかけに過ぎなかった。アメリカの大学に進むのではなく、日本の大学に進んで、もっと日本のことを知りたい。日本にいて、日本人として日本の勉強をしたい。そんな思いに自然となっていたことが自分でも信じられなかった。 個性を自然に受け入れてくれたあの環境が、僕のかたくなな心を、とても自然にほぐしてくれたのだろう。信じられないくらい「アメリカ一辺倒」、小生意気なアメリカナイズ少年だった僕は、高校1年の春以降、がらりと日本びいきに変身し、日本もアメリカも客観的に見つめられる自分でいたいと思うようになった。 そして高校2年の夏。7月下旬から1ヶ月間、クラスメイト全員でアメリカ語学研修に行き、僕も一緒に一時帰国。5日間の日本滞在の後、再び、今度は留学先にひとりで出発することになっていた。その5日間はめまぐるしく過ぎて行った。念願の、本当に心から願っていたアメリカ留学が始まろうとしているのに、全く実感が沸かなかった。そして迎えた当日。駅には沢山のクラスメイト、先生方、家族が見送りに来てくれた。いろんな感情が入り混じり、ある種の興奮状態でいた為、せっかく見送りに来てくれた人たちに対して、しっかりとした挨拶をすることもなく東京に向かう電車に乗った。嬉しいとか、悲しいとか、高揚感とか、何もなく、ただただ時間を生きている感じだった。貰った手紙を読みながら、切なさと高揚感が交じり出し、ろくな挨拶もせずに電車に乗った後悔が脳裏をかすめ、寂しそうにしていた母の顔が焼きついていた。 エピソード Vol.3へ |