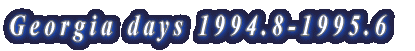
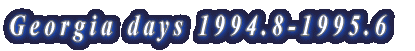
| 第30話 「秋の憂鬱」 |
| サンクスギビングの休みも終わり、また通常の生活に戻った。5日間の休みも、アラバマに行って退屈な時間を過ごし、家でも特に何事もなく淡々と過ぎて行った。デニーには「生活はどうだい?」と訊かれ、ベリーナイスと答えた。本心なのか本心でないのか、いまいち自分でも分からなかったが。 「同年代が家にいたらもっと楽しいはず」 「多くは望まないです」 「なんで?」 「PIEからは、いろんなファミリーがいると教えられている。この家の人たちはいい人たちだから、それだけでいいんです」 これはほとんど本心に近かった。ただ、手紙を書いたり勉強に多く時間を費やしていると、「沢山手紙書いてることは知ってるよ」などと言われ、居心地の悪さを感じていた。自由にさせて欲しかった。 クリスマスまでまだ1ヶ月もあったが、皆でクリスマスツリーを仕上げ、リビングに飾った。手のひらに乗るくらいのガラス球にそれぞれの名前が書かれたものもツリーにぶら下げた。勿論、その中には僕の名前の入ったガラス球もあった。 「コウが日本に帰る時は、自分のガラス球を持って返っていいよ」 デニーが言った。ところが、 「ダメよ!来年以降はこれを見て、コウを思い出すんだから」 ベリンダが嬉しいことを言ってくれた。 コーラスのクラスでは、クリスマス・コンサートに向けての練習が進んでいた。僕は4曲ピアノ伴奏をすることになっていたのだが、ホスト宅にピアノがない為、朝、授業が始まる前に音楽室のピアノで練習したり、また夜はベリンダの大学について行って、電子ピアノで練習をさせてもらったりしていた。 「あなたのピアノの音色、私たちが授業している部屋まで聴こえてくるのよ。クラスの皆に、あの音は私たちの家にステイしている日本人留学生のピアノよ、って自慢してるの」 僕とベリンダは行き帰りの車の中でいろんな話をし、特にベリンダはクリスマスに行くコロラドを心待ちにしていて、「あと何日!」と毎日カウントダウンをしていた。 でも毎日のように、小さいながらもイヤなことは起きていた。 僕が遣った電話料金は、明細書を見て計算をし、小切手でベリンダに渡していた。小切手には受取人の名前を書く欄があるのだが、そこにベリンダの名前を書いて渡した。ところがある日、ベリンダが仕事から帰って来ると、とても機嫌が悪く、何かと思ったら、ベリンダに渡した小切手をそのまま電話局に送ったのだそうで、当然の如く受取人がベリンダになっている小切手は受け取れないと電話局から知らせが届き、電話が止まっているというのだ。つまり、僕はベリンダの名前を書かずに、電話局宛か未記入のままにすべきだったのである。僕たちは一緒に電話局に行き、支払いを済ませ、電話も無事に通信可能になったが、よくよく考えたら、それはベリンダの不注意ではあるまいかと思った。ベリンダは僕を責めてばかりいたが、確認しないで小切手を送ったのはベリンダだし、受取人が違うのであれば送る前に僕に言うべきだったのではないか。僕はてっきり、電話代を全てベリンダが支払い、自分の分だけをベリンダに支払えばいいのだと思っていたわけで、まさかそれを電話局に送るなんて思ってもいなかったのだ。 お金に関しては、どんぶり勘定なところもあった。ピザを頼んで、お金が足りないから僕が代わりに払っておいたり、お金を先に渡して頼みごとをした分のお釣りも適当だったり、計算がちぐはぐになっていた。たかが数百円なのだが、何だかいい気分がしなかった。 「この間の分があるから、それで相殺しましょうよ」 と言われ、僕が数ドル足りないと言うと、「細かいことはいいじゃない!」と返される。良くないのだが、でも食事代にしても、小さな買い物にしても、ベリンダが払ってくれることもあるのだからまぁいいか、と思うことにしていた。 ベリンダとのそうしたやりとりは、最終的にはプラスマイナスゼロ(実際はベリンダの方が余分に払っているのだが)だったが、デニーは姑息だった。ベリンダがいないのをいいことに、一緒にビデオレンタルに行って僕に代金を支払わせたり、ビールを買わせて「ベリンダには内緒」と言ったり。今となれば、なぜ従順にも支払ったりしたのだろう?と思うが・・・。 ビデオレンタル店では店員の女に、デニーのいる前で「この町は好き?」「日本より?」と訊かれてムッとした。この類の質問は一年中続いたが「日本よりも好きか?」と訊かれると心はかなり拒否反応を起こした。こんな野蛮な国・・・と心の奥底では思っていた。デニーは女店員に、「彼は勉強、手紙、電話ばかり」とイヤそうな顔で話していた。翌日はベリンダはアラバマに行き、デニーは仕事だったのでひとり気ままな時間を過ごしていたが、デニーが帰ってきてからはずっとテレビを観ていた。あまりにも暇だった。勉強することも手紙を書くことも出来ない。好きにさせてくれ!と心の中で叫んでいた。最近デニーの機嫌が悪い。ホストが家にいると不自由な感じが否めず、放課後、スクールバスの中から家の前にホストの車を見つけるとガックリしていた。デニーが機嫌の良い日は、ベリンダの機嫌が悪かったり、何だかいつもホストに振り回されているような気がした。ロレインに相談しようかとも思ったが、ためらわれた。これといって、何を相談すればいいのかも分からなかった。 放課後のスクールバスの中では、たまに、丸めた紙を投げ合って遊んでいる周囲に辟易することがあった。あまりにも子供じみているように思えた。アメリカの高校生は日本の高校生よりも大人っぽいとよく本に書いてあったが、とんでもないと思っていた。 この国がどんどん嫌いになっていくようで恐かった。これといった特色ある文化もなく、rude(無礼)な人々が多くいるように感じた。大好きだった英語も、日常コミュニケーションの手段となると、どうも味も素っ気もなく、言葉というよりは「暗号」のように感じて、英語を話すこと自体、イヤになりそうだった。 第31話へ |