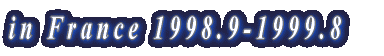
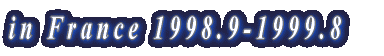
| 第1話 「ストラスブールに到着」 |
| 1998年9月6日(日)。パリのホテルで12時間も寝てしまい、逆に寝疲れ。語学研修地、ストラスブールに向かう為、重いスーツケースを引きずってパリ東駅に向かった。当時はまだパリ−ストラスブール間はTGV(超特急列車=フランス版新幹線)が開通しておらず、鈍行で4時間かけての道のりだった。日曜日ということもあってか、凄まじい混み具合。予約席は取れず、自由席も満席。仕方ない、通路に座るしかないかと思っていたら、僕の側にいた女の子2人組と目が合った。 「混んでるね。もう席ないよね」 と話しかけられた。彼女たちはこの混雑した電車の中、座れる席があるかも知れないからと言って、なんと探しに行った。こんなに混んでるんだから無理だろうと僕は思っていたのだが、程なくして1人が戻ってきて、「3人分の席を確保したから、来て!」と僕に言うではないか!なんと!まだ出会って数十分だというのに、こんな親切をされて僕は感激した。 2人のうち1人は、僕の留学先であるブザンソンで生まれたと知り、僕は大興奮!彼女たちは大学1年生で英語専攻。イギリスに留学したいと言い、僕と同じく外国語専攻で、しかも留学希望を持っているということで、話は盛り上がった。この頃、僕の語学力はまだフランス語よりも英語の方が自由だったが、フランス語を勉強しに来ている僕のことを考えて、彼女たちはフランス語で通してくれた。さすがにぐったり疲れたが、いい訓練にもなり、あっという間の4時間だった。 ストラスブールでの1ヶ月間はホームステイをすることになっていた。駅にはマダムが迎えに来てくれた。年は60代前半の未亡人で、既に歯科医を引退し、3人の子供たちと暮らしていた。子供たちといっても、勿論もう30をとっくに過ぎている男2人と女1人で、3人共独身だった。この家には常に留学生がステイしているとのことで、現在はアメリカ人マイクが居ると言う。それを聞いて、顔が引きつった僕・・・。マダムは笑いながら、 「フフフ・・・あなたが何を思ったのか分かるわよ。まぁ、大丈夫よ」 と僕を諭した。 家は中心街から少し外れた住宅街にあった。大きな邸宅で、玄関を入ると仏教のものと思われる大きな彫刻品があった(仏教を信仰しているわけではないようだったが)。留学生用の部屋は3つあり、そのうち1つはマイクが使っているから、2つの中から選ぶよう言われた。驚いたことに、僕が到着した日、1通のハガキが僕宛に届いていた。大学の同級生ポン子からだった。ポン子は僕と同時期にフランスに発ち、ポワチエという町に留学していた。僕よりも一足先にフランス入りしていたポン子は、ハガキで状況を知らせてくれた。まさかストラスブールに着いた初日にハガキを受け取るとは思ってもいなかったので、嬉しい驚きだった。 この日、家ではパーテーが行われていた。僕が家に着いた時点ではもうお開きになっていたのだが、帰ろうとしていた最後の1組は、マダムと同様にいつも留学生を受け入れている方で、ノルウェー人の女の子を伴っていた。北欧に大いなる憧れを抱いている僕は、ノルウェーと聞いて目が飛び出んばかりの喜びようだった。しかも、翌日から僕と同じ学校に通うと言う。 マダムはとても優しく穏やかで、話好きで品のいい料理好きの人だった。この日の夕食はクスクスだった。僕はクスクスが苦手だったのだが、この日から大好きになった。これからの1ヶ月、このマダムの一流レストランにも負けず劣らない手料理を堪能出来ると思うと、ワクワクした。 この日、マイクは出かけていて家には居なかった。マダムの娘バルバラは看護婦をしているということを予め聞いていたが、「看護婦」という職業と、マダムの性格から、天使のような人を想像していたが、無残にも打ち砕かれた。男勝りの性格で、それどころか、笑顔ひとつ見せない、人を震え上がらせるのが大の得意とでも言うような・・・無愛想な人だった。この人が本当に看護婦なのだろうか、と僕は我が目を疑った。言葉遣いも荒々しい感じだったのだ。熱心に僕に話し掛けてコミュニケーションをとろうとするマダムとは逆に、留学生なんてちっとも興味ないとばかりに、僕には目もくれない彼女を少し恐く思った。 明日からはいよいよ学校が始まる!マダムは「CIELという学校はとてもいい学校よ。あなたの語学力が飛躍的にアップすること間違いなし!」と太鼓判を押してくれた。どんな人たちと出会えるのだろう。しかし僕はどことなく心細さを感じていた。1年半前にカンヌで過ごした1ヶ月間のことをしきりに思い出すのだった。南仏の太陽そのものというくらいに、明るく賑やかな1ヶ月間だった。あらゆる国から集まった人たちと友達になって、毎日ワイワイしていた。あの空気感はやはり南仏という土地柄から来るものだったのだろうか。・・・悪い癖だ。あの時はあの時。今は今。過去の楽しいことを思い出して感傷に浸るのは良くない。僕は、夏も終わり秋に近付いているこのストラスブールという街の片隅で、ちょっとした孤独感を味わっていた。 第2話につづく |